――夜勤のナースステーション。
深呼吸を3回してから病室へ向かうと、さっきまでこわばっていた患者さんの表情が少しだけ緩みました。こちらの落ち着きは、必ず相手に伝わる。私はその瞬間を何度も見てきました。ストレスは消せなくても、安心に変えることはできる――これはベッドサイドで学んだ、いのちの現場の真実です。
ストレスは「敵」ではなく「合図」。合図に丁寧に応えると、安心は何度でもつくり直せる。

「不安があるからダメ」ではありません。
ストレスは、心と体が「大切なものを守りたい」と知らせてくれる合図です。合図には手順で応えるのがいちばん早い。看護師として私が現場で繰り返し使い、どなたでも今日から始められる“安心の手順”は次の3つです。
- 呼吸を整える(吐く息を長く)
- 体を整える(姿勢・筋肉・環境の三点)
- 意味を整える(言葉と視点のリフレーム)
この順番は、炎上した心を上から押さえつけるのではなく、下から静かに支える方法です。
神経は“下り坂”でしか減速しない。だから「吐く息 → 体 → 言葉」の順が効く。

1) 呼吸がブレーキ
不安や怒りで交感神経が優位になると、心拍は上がり、呼吸は浅く速くなります。ここで吐く息を長くするだけで、副交感神経に“ブレーキ信号”が送られます。脳へ直接「今は安全だよ」と知らせる、もっとも素朴で強力な方法です。
2) 体の姿勢が感情を決める
肩をすくめ、視線が下がると、脳は「危険だ」と判断します。反対に、肩幅に重心を落とし、胸をひらくと、筋紡錘や関節受容器が「安定」の情報を返します。体は嘘をつきません。
3) 言葉は方向舵
呼吸と姿勢でスピードを落としたら、言葉で向きを決める番です。
「どうしてこうなった?」よりも、「私は今、何ができる?」。
問いを変えるだけで、脳内ネットワークの使われ方が変わります。看護記録でも、問題の列挙ではなく次の一歩を必ず書きます。言葉は行動の設計図です。
ベッドサイドから生まれた“安心のレシピ”

例1:眠れない夜の90秒プロトコル
夜、考えが止まらない時に。ベッドサイドで何度も一緒にやってきた手順です。
- 息を吐き切る(6秒)
- 吸う4秒 → 止める2秒 → 吐く8秒 を3セット(計42秒)
- 肩を後ろに回し、胸の中央を指で軽くトントン(10回)
- 心の中で**「いまは安全。私は眠り方を知っている」**と1回だけ唱える
- 目を閉じ、頭上からやわらかな光が背中まですーっと下りるイメージ(30秒)
90秒で神経は“戦闘モード”から“回復モード”へ。
朝になっても不眠が続く場合は、同じ手順を昼の仮眠前にも使います。夜だけに戦わないのがコツ。
例2:職場で胸がざわついた時の「姿勢リセット20秒」
- 足裏を床に(指先を少し開く)
- 骨盤を1cm前へ(腰を反り過ぎない)
- 息を鼻から3秒吸って、口から6秒吐く ×2回
- 目線をモニターから30度上へ移し、遠くの壁の一点を見る
たった20秒。けれど驚くほど言葉の選び方が変わります。
ナースコールが重なったときも、この20秒を挟むだけで「次に安全が必要なのは誰?」と判断できるようになります。
例3:感情の波にのまれそうな時の「ノート3行」
- 事実:起きたことを1文だけ(例:メールで指摘を受けた)
- 解釈:自分の考え(例:私は役に立てていない)
- 選択:今日できる1歩(例:事実を確認し、10分で修正案を送る)
私がカンファレンスで後悔した日、救ってくれたのはこの3行です。
「事実」と「解釈」を分けると、感情は扱えるサイズになります。
例4:家族の看取りに寄り添った娘さんの言葉
最期の夜。娘さんは震える手で母の手を包みこんで言いました。
「お母さん、ここにいるよ。呼吸を合わせよう。吸って、吐いて――」
二人の呼吸は少しずつ同じリズムになり、硬かった額のしわがほどけていきました。
安心は移る。だれか一人が呼吸を整えると、空間の空気が変わるのです。
あの夜、私たちは涙を拭きながら確かに感じました。**“いのちは落ち着く方向へ向かう力を持っている”**と。
例5:怒りで爆発しそうな時の「手放しスクリプト」
- 一度、背もたれに体重を預ける
- 息を3秒吸い、8秒吐く
- 心の中でこう唱えます。
「私は反応を選べる。今は“守る言葉”を選ぶ」 - それから短く事実だけを伝える。「今は処置中です。3分後に必ず説明します」
看護現場では、限られた時間の中で誤解が生じることもあります。
怒りの炎に油を注がず、**“守る言葉”**を使うと、状況は驚くほど早く落ち着きます。
今日から始める「安心をつくる5分間ルーティン」

- 1分|体を整える
肩を3回後ろ回し、首を左右へゆっくり倒す。背中を壁に当て、後頭部・肩甲骨・お尻を軽くタッチ。体に「ここが安心の姿勢」と覚えさせます。 - 2分|呼吸を整える
4秒吸う→2秒止める→8秒吐く ×5セット。吐く息でお腹をぺたんとへこませるイメージ。 - 1分|意味を整える(アファメーション)
声に出さず心の中で3回。- 「私は今、落ち着きをつくっている」
- 「完璧でなくていい、前進を選ぶ」
- 1分|未来を選ぶ
今日の「小さな一歩」を手帳に1行。終わったら✓を付ける。脳は完了の印で快感物質を少し放出します。
この5分を朝と夜に。3日で体感が、7日で習慣が、21日で性格のように感じられる“基礎”ができます。
7日チャレンジ:安心の筋力を育てる

- Day1 呼吸:4-2-8呼吸を合計3分
- Day2 姿勢:壁タッチ30秒 ×3回
- Day3 言葉:「私は反応を選べる」をメモして持ち歩く
- Day4 環境:寝室の光と温度を“少し暗く・少し涼しく”
- Day5 手放す:未読メールを10件だけ処分
- Day6 感謝:寝る前に「ありがとう」を1つ書く
- Day7 統合:5分ルーティンを朝夜で実施、1週間の変化を3行で記録
“続けられた日数”ではなく、戻って来られた回数を誇りにしてください。人は何度でもやり直せます。
心が折れそうなときの「看護師のひとこと」

- 「つらいときは、呼吸を小さくゆっくり」
体が受け止められるだけ、で十分です。 - 「助けを求めるのもセルフケア」
SOSは弱さではなく戦略です。 - 「眠れない自分を責めない」
眠気は“借金”のように返ってきます。今日は横になれた、その事実だけで合格。
小さな科学のメモ(やさしい説明)

- 吐く息が長い=迷走神経が刺激されやすい
心拍の揺れ(HRV)が整い、落ち着きモードに入りやすくなります。 - 姿勢と視線が情動に影響
目線を上げる・胸をひらくだけで、脳は「安全」を検知します。 - 言葉は注意の向きを変えるスイッチ
「できない理由」から「できる一歩」へ。使う言葉を変えると、選択肢が見えます。
むずかしい理屈は覚えなくて大丈夫。“吐く息長め・胸ひらく・前向きな一言”――この3つをセットで思い出してください。
安全のためのしるし(専門家へつなぐ目安)

- 2週間以上つづく不眠、食欲の大きな変化、日常生活が保てない程の落ち込み
- 頭痛・胸痛・息切れなど強い身体症状が繰り返し起きる
- 「消えてしまいたい」などの思いが頻繁に浮かぶ
セルフケアと医療・相談機関の支援は両立します。遠慮せず、早めに相談してください。あなたの速度で、確実に楽になります。
安心は“贈り物”ではなく“つくる技術”。あなたはもう、やり方を知っている。

ストレスが来たら合図に感謝し、
吐く息を長く、体を整え、言葉で向きを決める。
この順番を、何度でも。失敗しても、やり直すたびに安心の筋肉は太くなります。
最後に、ベッドサイドで出会ったたくさんの手の温度を思い出します。
震えていた手が、呼吸を合わせるうちに温かくなる。
その変化は、いつもあなたの中から始まりました。
今日のあなたに、たった一つのお願いです。
今、この瞬間の息をゆっくり吐いて、胸をひらいてください。
その一呼吸が、あなたの世界をやさしく整えます。
そして心の中でそっと――
「私は反応を選べる。私は安心をつくれる」。
ここからまた、一歩ずつ。
いつからでも変われます。あなたのペースで、大丈夫。
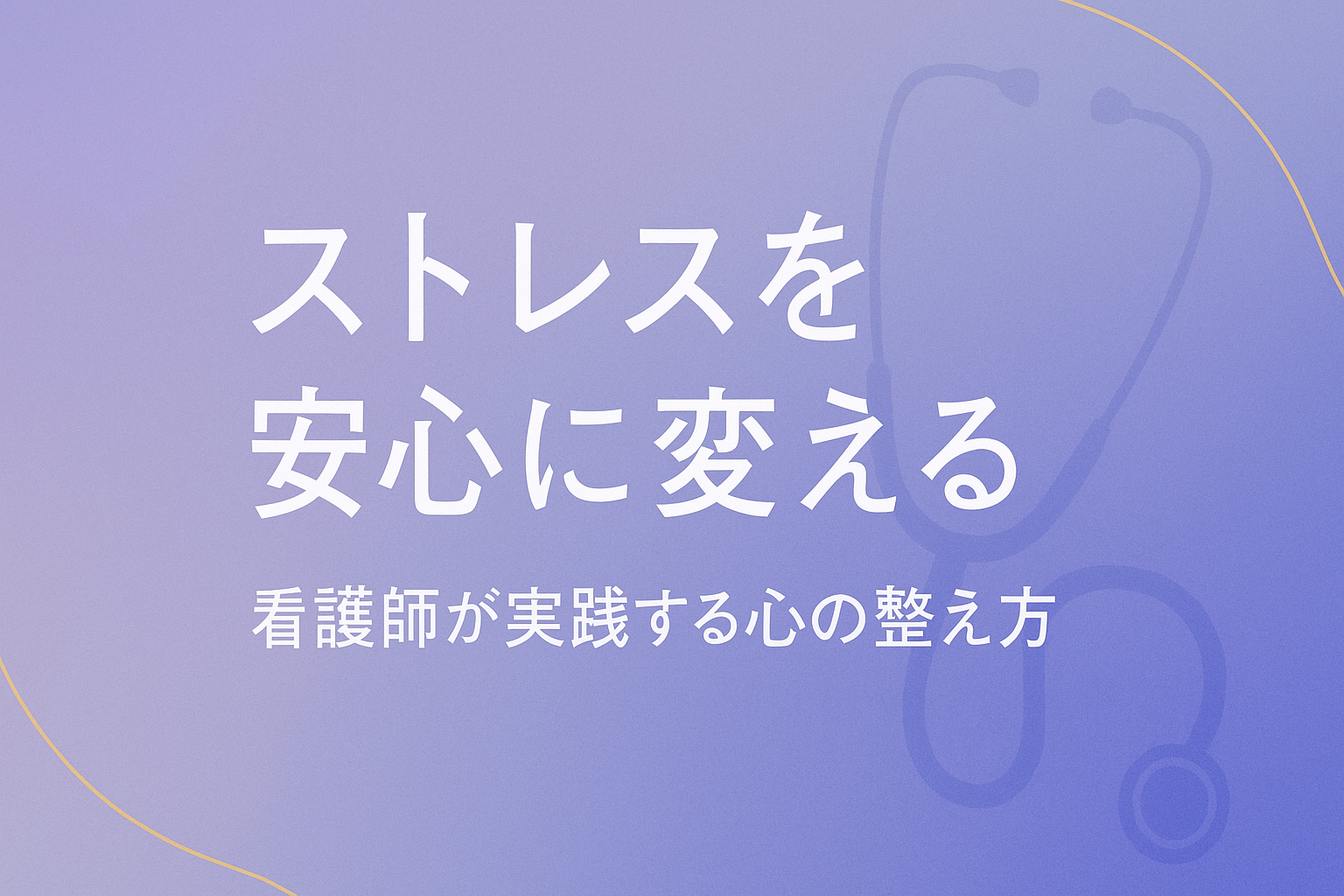
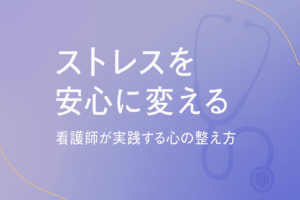
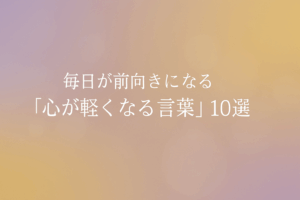
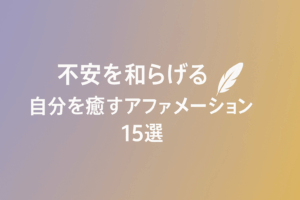
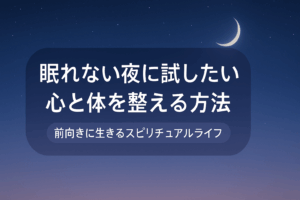
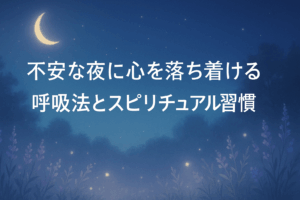
コメント